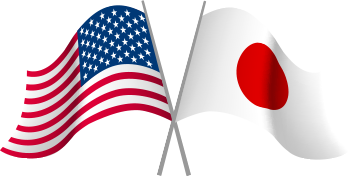広島日米協会は7月4日、広島市中区のリーガ・ロイヤルホテル広島で2025年度理事会・総会と、講演会・懇親会を開いた。理事会・総会では24年度事業報告と決算、本年度事業計画案と予算案をいずれも全会一致で承認し、新たに理事3人を選出。講演会・懇親会には66人の会員が集った。
24年度事業では、昨年7月の理事会・総会に続いて10月に「秋の講演と交流の夕べ」、12月に「クリスマス・忘年の夕べ」を開催した。3月末現在で法人会員52社、個人会員61名。決算は366万8500円の収入・支出で、臨時会費の値上げや3月の会合を取り止めるなどの収支改善策により2年ぶりの黒字決算となった。
本年度の事業計画は、10月に「講演と交流の夕べ」、12月に「クリスマス・忘年の夕べ」を開催する予定。引き続き物価高騰に対応するため年会費は2000円値上げし、予算は収入・支出がそれぞれ総額415万1121円となった。
新任の理事は、谷本康成氏(マツダ・コーポ―レート業務本部総務部長)▽坊田和彦氏(広島信用金庫常務理事)▽今村司氏(広島テレビ放送代表取締役社長)
講演会では、広島市立大学平和研究所教授の梅原季哉氏が「被爆80年 核兵器をめぐる『ルール』のグローバルな現状」の演題で話した。
世界では現在、9カ国に1万2241発の核兵器があり、冷戦期のピークの約7万発からは大幅に削減されたものの、削減スピードが落ち、中国では増強中であることなどを説明。核兵器をめぐるルールとして、①核のタブー②核不拡散規範③核実験禁止規範④核軍縮規範⑤核廃絶・核兵器禁止-があり、「核抑止論や先行不使用などの発想から広島・長崎への原爆投下後は危うい局面もあったものの使用されてこなかった」と述べた。
その一方で、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエルのガザ地区での紛争、米国やイスラエルによるイランへの空爆など核をめぐる現状が揺らいでいる状況を解説。「核軍縮義務が果たさず、核による威かくも禁止されるなど、核を保有する国も保有しない国も、双方とも現状に不満を抱えている。日本は唯一の被爆国としての意味をよく考えて行動してもらいたい」と訴えた。
懇親会では、山本一隆会長が「今後ともみなさんと共に日米交流に努めていきたい」とあいさつ。乾杯で祝った後、会員相互の交流を楽しんだ。